野菜のひみつ
きゃべつの生まれ故郷
きゃべつの生まれ故郷はヨーロッパ大西洋岸と地中海沿岸の地域と言われており、日本へは、18世紀初めにオランダ人によって長崎に持ち込まれました。きゃべつは現在のような球の形ではなく葉きゃべつで、見て楽しむきゃべつ「葉ぼたん」として日本に広まりました。19世紀になり、今のような球の形のきゃべつが日本に伝わり、食用のきゃべつが広まりました。

きゃべつは医者
ヨーロッパで、きゃべつは「貧乏人の医者」と呼ばれるほど、昔から体に良いと言われていました。紀元前4世紀ごろの古代ギリシャを代表する医学者で、西洋医学の父と言われているヒポクラテスは、きゃべつを「腹痛と赤痢(せきり)の特効薬」として、食べることを勧めています。また、紀元前1世紀ごろの古代ローマ政治家の大カトーは、「ローマ人が何世紀もの間、医者なしでやってこられたのは、きゃべつのおかげである」と言っています。

きゃべついろいろ
-

-

普段、お店でよく見かけるきゃべつが、この寒玉きゃべつです。「冬きゃべつ」とも呼ばれています。しゃきしゃきとした食感が特徴で、生で食べるのも美味しいですが、煮物や炒め物、お好み焼きにも向いています。
-

-

みずみずしくやわらかいのが特徴で、生で食べたり浅漬にも向いています。
-

-


フランスのサヴォワ地方で作られていたため「サボイきゃべつ」と呼ばれています。葉の表面の縮れが、絹織物のちりめん(細かな凹凸があることが特徴)に似ていることから、「ちりめんきゃべつ」とも呼ばれています。葉の水分が少なくかためなので、生で食べるよりロールキャベツなどの煮込み料理やスープに向いています。
-

-

「赤きゃべつ」「レッドきゃべつ」とも呼ばれています。紫色はブルーベリーやぶどうにも含まれるアントシアニンという色素で、ゆでると色素がゆで汁にでてしまうため、生で食べたり、マリネや酢漬に向いています。また、マリネや酢漬にした際、酸性であるお酢やレモン汁が加わるので、紫から赤色やピンク色へと変化し、鮮やかな色になります。
-
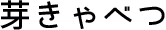
-

大きさが3~4㎝の小さいきゃべつで、一つの茎に50~60個くらいなるので、「子持ち甘藍(こもちかんらん)」とも呼ばれています。かたくて少し苦みもあるため、ポトフやパスタなど煮込み料理や炒め物に向いています。
-

-

たけのこのような形をしているきゃべつです。葉は少し厚めでやわらかく、生で食べるのに向いています。
おいしいきゃべつの選び方
- 寒玉きゃべつ
- 葉の巻きがしっかりしていて、重量感のあるもの。
- みずみずしい外葉がついているもの。
- 軸の切り口が新しく、太すぎないもの(500円玉くらいの大きさが目安)。
- ツヤがあり、緑色が濃いもの。
- 春きゃべつ
- 葉の巻きがゆるく、軽いもの。
- みずみずしい外葉がついているもの。
- 軸の切り口が新しく、太すぎないもの(500円玉くらいの大きさが目安)。

-

-
ざく切りにしたきゃべつを、塩、しょうゆ、昆布など合わせた調味料と混ぜ合わせて、軽く漬けます。
-

-
北海道・東北地方の冬の保存食です。乾燥した身欠きにしんを米のとぎ汁で戻したものときゃべつ、大根、にんじん、生姜、唐辛子などを塩、米麹で漬けて発酵させてつくります。
-

-
ドイツの代表的なきゃべつの漬物です。千切りしたきゃべつを塩で漬けて発酵させてつくります。



