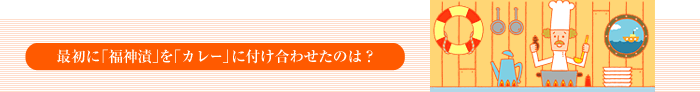 |
「福神漬」がはじめて「カレーライス」に添えられたのは、1902(明治35)年頃、ヨーロッパ航路船の食堂だとか。食堂のカレーにはインドや東南アジアでカレー料理に添えて食べる「チャツネ」が付け合せとして添えられていましたが、あるときチャツネが切れてしまいました。そこで代用品としてコック用の福神漬を付け合せたところ、大評判になりました。
西洋化を押し進めていた当時の日本、ハイカラな外国船航路の1等食堂のスタイルはあっという間に巷(ちまた)に広がっていったのです。 |
|
 |
 |
インドではスパイスを使った料理はすべてカレー。付け合せもいろいろありますが、その代表は「ピックル」と「アチャール」です。「ピックル」は、青唐辛子やライム・トマト・しょうが・熟していないマンゴーなどを、赤唐辛子・マスタードオイルと酸味・防腐効果の高いピックル液に漬け込んでつくるもの。西洋のピクルスと呼び名は似ていますが、酸っぱさは少なく激辛&スパイシーです。
「アチャール」は、野菜や果物をスパイス・香辛料・酢と一緒に漬け込んだもの。大根、ジャガイモ、トマト、にんじん、たまねぎ、キャベツ、唐辛子、にんにくなど、なんでもアチャールになります。 |
|
 |
 |
| カレーは姿形を変えて、東南アジアやアフリカなど世界各地で食されています。東南アジアではレモングラス・コリアンダーなど生のハーブを使って、独特の香りと爽やかさのあるカレーに仕立てます。付け合せの定番は「ラッキョウ」。日本でラッキョウを付け合せるのはここからきたという説もあります。アフリカ東部のエチオピアでは、赤唐辛子ベースの辛口スープで煮込んだワット(おかずの意味)というカレーに似た料理があり、ローズマリーなどハーブで味付けた薄味の肉野菜炒めを付け合わせます。 |
|
 |
 |
「福神漬」は、明治時代の初め頃に考案、製造されたと言われています。それまでは塩漬けだった漬物をしょう油で漬け、味の良い福神漬になるまでに約10年もの歳月を要したと言われていますが、その甲斐あって福神漬はまたたく間に庶民の間で評判となりました。
その後、軍用食として採用されたことも手伝い、全国へ広まっていきました。 |
|
 |
 |
いかにもおめでたい名前の「福神漬」。名付け親は、明治時代の流行作家・梅亭金鵞だと言われています。その由来は諸説ありますが、7種類の野菜が入っていることや、福神漬を考案した店の近くに七福神が祀られていたことから考えついたという説が有力です。
また「おかずがいらないほどおいしい」ため、食費が浮いてお金がたまるので「福の神も漬けてある=福神漬」と言われるようになったとも伝えられています。 |
|
 |
|



